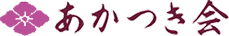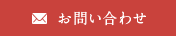中国(唐)より雅楽の演奏用として、伝来した13弦の弦楽器。
現在では、「おこと」と呼ばれ、お正月にはテレビなどからその音色をよく耳にします。
繊細な美しい音色を特徴とし、比較的演奏しやすい楽器です。
もともとは貴族階級の楽器でしたが、江戸時代からは武家・裕福な市民階級にまで広まり好まれました。
現在、最も一般に普及している邦楽器と言えます。
竜に似せられ作られた楽器
13本の弦が張られていて、可動式の柱〔じ〕という駒〔こま〕を立てて音の高さを調整します。
筝の各部には竜の名前が付けられています。
それは筝が高貴な生き物と崇められていた竜に似せて作られた事に由来しています。
現在では生田流、山田流の二派に分かれており、流派によって構える姿勢・つけ爪などに違いがあります。また、当会は生田流です。
ちなみに、「筝」と「琴」を混同しがちですが、「筝」は柱を持っているもの、「琴」は柱のないものと区別し、日本には「琴」はほとんど絶えてしまっています。
唐から伝わった楽器
筝は奈良時代直前に中国(唐)より日本に伝わり、当初は雅楽の楽器の一つとして使用されていました。
その後、雅楽だけでなく、筝曲〔そうきょく〕として演奏されるようになりました。
筝曲の発祥は筑紫〔つくし〕流といわれています。
これは、雅楽から影響を受けて、室町時代末期に大成しました。
そして、17世紀に八橋検校〔やつはしけんぎょう〕という音楽家が、それまで貴族・武士・僧侶の音楽であった筝を芸術音楽へと発展させ、庶民などたくさんの人々が弾くことが出来る楽器にしました。
琴の歴史

筝(琴)は奈良時代直前に中国(唐)より日本に伝わり、当初は雅楽の管弦楽奏用楽器の一つとして使用されていました。
日本における筝曲の発祥は筑紫流といわれています。これは、九州久留米の善導寺の僧侶賢順が雅楽と琴曲(きんきょく)の影響を受け、筝(琴)の音楽を室町時代末期に大成させたものです。
17世紀に八橋検校が現れ、この検校を始祖として現在のような筝曲が発展し、三味線同様いろいろな流派が生まれました。現在では生田流、山田流の二派に分かれております。
琴はそれまで三味線の伴奏としてしか使われていなかったのですが、18世紀に江戸の山田検校が独奏楽器として琴の曲を作りました。
同時に琴師重元房吉が、琴にさまざまな改良を施しました。
長さを6尺に、厚みより持たせ、縦方向のソリを強くして音量の増大を図り、なおかつ、琴爪を大きくしたので音質も明瞭になりました。
その製作技術、技法は今日まで伝えられ、山田流、生田流を問わず広く使用されています。
弦を弾いて響かせる
筝の胴部分は、桐の木をくりぬいたものに裏板がはられており、裏板の両端に音穴〔いんけつ〕という二つの穴が開いています。
中の空洞部分で音を響かせる構造になっています。
筝の基本的な奏法は、右手の親指、人差し指、中指に義甲〔ぎこう〕(つけ爪のようなピック)をはめ、弦を弾いて演奏します。
流派によって違いがあります。
生田流
四角い爪を使用。筝に対して斜めに正座して座り構える。
山田流
丸い爪を使用。筝に対して真っ直ぐに正座して座り構える。